| 2017 | 2016 |
このハスは、昭和二六年(一九五一)に元東京大学検見川厚生農場(現東京大学総合運動場)内から発掘された古代ハスで、当時ハス博士として知られた大賀一郎博士の発見により大賀蓮と名づけられた。発掘は、湧水や雨に苦しめられながらついに地下六メートルの青泥層中から三個のハスの種子を発見し、博士の発芽処理により三個とも発芽することに成功した。この内一個は蓮根ができるまでに生長し、紅色系の大型の花が開花した。ハスの種子は一定の条件下では驚くほど長く生き、大賀博士が南満州のフランテンで発見した種子は約千年前と、神崎町滑川で須恵器の中から発見された種子も約一二〇〇前と推定され、いずれも発芽している。この事実から大賀博士は、昭和二二年(一九四七)に丸木舟が出土した東大農場に着目し、発掘に取りかかった。発掘には千葉市立第七中学校(現花園中学校)の生徒約四〇人も加わり、着手後二〇日あまり経過してハスの種子が発見された。現在、大賀蓮は、日本をはじめ、西ドイツ、アメリカ、中国など各国で栽培され、紅色系の大型花をもつ観賞用ハスの一品種として知られている。《検見川の大賀蓮 昭和二九年三月三一日 県指定天然記念物》



















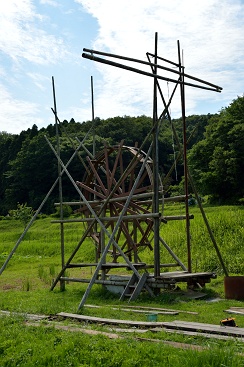

季節の風物詩 大賀蓮
※ハス見本園 - 東大生態調和農学機構
東京大学ハス見本園は、西東京フィールド・生態調和農学機構の観賞用ハスに係る教育研究施設です。園内には作出した種を含む二〇〇種以上が展示・保存されており、開花時期の六月下旬から七月に一般公開と観蓮会を開催しています。